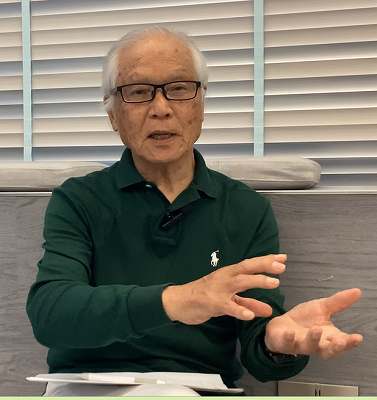投稿日:2025.10.24 最終更新日:2025.10.24
グリーンウォッシングからグリーントラストへ -サステナブル企業は「人の言葉」で語るべき理由- by Antti Isokangas
この記事を書いた人
NECSUS STAFF

サスビズ時代のあらゆるステークホルダーとのコミュニケーションで気を付けるべきことは何か?第一人者が世界の潮流から最適解を示します。
環境やサステナビリティを企業がどう語るか?
人々の目はかつてないほど厳しい。あいまいな約束や派手な宣伝に人々は疲れ、耳を貸さない。今や、サステナビリティの伝え方は、企業にとって最大の武器とも、最速の失敗要因ともなりうるのである。
信頼の欠如は政治だけの問題ではない
世界中で人々は政府やメディアへの信頼を失っている。一方、企業は社会で最も信頼される存在へとなりつつある。ただこれは、企業が急に「聖なる存在」となったからではない。他の選択肢が弱体化しているからである。人々は依然として企業の実行力を信じている。企業は「行動する」だけではなく、「社会の信頼を生む方法で伝える」責任を負っているのである。
調査によれば、人々は政府やメディアよりも「自らの勤務先」を信頼する傾向が強い。人々が求めているのは、本物らしさ、行動、そして希望である。だからこそグリーンウォッシングは、倫理やマーケティング上の問題にとどまらず、経営戦略としても重大な失敗を招く要因である。
コミュニケーションはサステナビリティそのものである
サステナビリティの発信は付け足しではない。一枚のパンフレットでも、一度きりのキャンペーンでもなく、それ自体が社会に与える影響の中核なのである。信頼を構築し、期待を形づくり、組織文化を育て、行動を社会へと広げる力を持つ。
重要なのは「感心させること」ではなく、「理解されること」である。過度な演出や巧妙さを狙うと、人々は離れ、あるいは批判するのである。
グリーンウォッシングからグリーンハッシングへ
グリーンウォッシング(環境配慮を誇張すること)は広く知られている。しかし近年は、グリーンハッシングという新たな問題が広がっている。これは、企業が実際に持続可能な取り組みを行っていても、「批判されることを恐れて語らない」現象である。
その結果、信頼の空白が生じ、声だけ大きい表面的な企業が注目を集め、本来リーダーであるべき企業が沈黙してしまうのである。沈黙は中立ではなく、責任放棄である。
企業がなすべきこと
では、企業はどのように行動すべきか。優れた実践から導かれる原則は以下の通りである。
【戦術ではなく真実から語る】
小さな取り組みであっても正直に伝える。ごまかしや誇張よりも誠実さが信頼をもたらす。
【約束ではなく成果を示す】
「2050年にカーボンニュートラル」といった未来目標だけでなく、「今期どのような成果を上げたか」を示す必要がある。意図より証拠、野心より実績である。
【人間の言葉で語る】
専門用語に満ちた表現ではなく、人々が日常で理解できる言葉を使う。ユーモアや謙虚さ、正直さの方がはるかに届きやすい。
【不完全さを認める】
すべてを解決したかのように装うよりも、試行錯誤や課題を共有する方が信頼を得られる。
【地域に根ざし、世界につなげる】
環境問題は地球規模だが、信頼は地域から築かれる。排出削減を語る際には、その成果が地域の生活にどう影響しているかを具体的に示すべきである。
結論
人々は不安や迷いを抱えているが、必ずしも冷笑的ではない。多くの人々は「変化は可能だ」と信じたいのである。
企業がサステナビリティを誠実に伝えれば、単に信頼を得るだけでなく、社会全体の自信を取り戻すことに貢献できる。
完璧である必要はない。しかし、自社が「何を大切にし、何を守るのか」を明確にし、誠実に発信することが不可欠である。静かだが確かなコミュニケーションの力は、単なる戦略ではなく、リーダーシップそのものである。
環境やサステナビリティを企業がどう語るか?人々の目はかつてないほど厳しい。あいまいな約束や派手な宣伝に人々は疲れ、耳を貸さない。今や、サステナビリティの伝え方は、企業にとって最大の武器とも、最速の失敗要因ともなりうるのである。