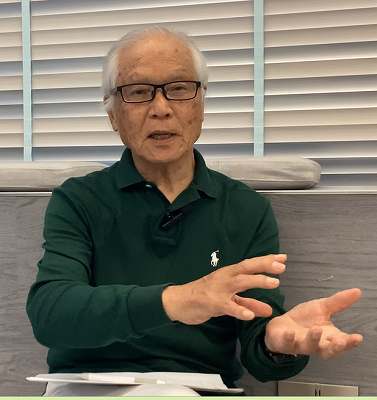投稿日:2025.10.24 最終更新日:2025.10.24
「待ったなし!サステナビリティ経営への変革」 特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラム 理事・特別顧問 後藤敏彦氏インタビュー
この記事を書いた人
NECSUS STAFF

9月20日にオンライン開催したNECSUS特別セミナーでは、「待ったなし!サステナビリティ経営への変革」と題し、特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラムの後藤敏彦=理事・特別顧問にご登壇頂きました。
以下、セミナー後の紙上インタビューです。ご覧ください。
Q1. 日本でサステナブル経営が広まる中で、今後課題となりそうなのは何でしょうか? 海外との比較を含め、お気づきのことがあれば教えて下さい。
A1. 経営層とマネジメントに関わる課題に関しては2.にまとめます。以下は今後課題になりそうなことを例記してみました。
①日本社会での「人権」認識と世界の「人権」認識にかなりズレがあること。良し悪しの問題ではないので、認識にずれがあることの認識の普及が課題。
② 日本は「失われた30年」といわれるように産業資本主義からポスト・インダストリアル社会への対応が遅れている。個々の企業の業種・業態で対応は異なるが待ったなしの状況にある。経済システムのダイナミックな動きの認識向上が必要。
③ サステナビリティ課題はダイナミック(流動的)である。世界が動くにつれ次々に新しい課題が生まれてくる。あえて2つだけあげておく。
ひとつは、平和への対応課題。世界が益々平和でなくなりそうなとき、個々の企業では如何ともしがたい課題であるが、状況が悪くなればなるほど何らかの対応が求められる。
もうひとつはAIの問題。生成AIは単なるコンピューター(ツール・道具)では無い、既にこの1~2年でツールからパートナーというかメンバーというか人間に替わって仕事の中核になりつつある。日本はDXと言いながら単なるデジタル化に止まっており、トランスフォーメーションとはほど遠く、生成AIどころではないといってもよい状況かもしれない。AIとの付き合いは米国や中国とは大きく遅れているようである。
Q2. 企業がサステナブル経営にプロアクティブに取り組むため、ビジネスリーダーにはどのような資質、スキル、態度が求められるか?
A1. 経営層・ビジネスリーダーの課題と、マネジメントの課題を分けます。
① 経営層、ビジネスリーダーの資質、スキル、態度
これには無数の経営指南書が出ている。それを読むとスーパーマンにしか経営ができないことになってしまいかねない。あえて2つだけあげておく。
ひとつは、歴史に関する深い認識・洞察力である、哲学ともつながるが。歴史は同じ通りには繰り返さないが、変化の時代には洞察力の基盤には歴史観と哲学は必須である。
ふたつめは多様な人材を束ねて成果に結びつけるマネジメント力である。束ねる組織の業種・業態、その組織の歴史などにより必要とされるマネジメント力は一様ではない。いずれにせよ多様性マネジメントがキーである。ティール・グリーン・オレンジ・アンバー・レッド組織、どれもあり得るし、一つの企業の中でも目的により何が良いかは簡単なことではない。
② マネジメントの課題
最初に、マネジメントは管理(コントロール)とは違う。ガバナンスの原義は「舵取り」であって「統治」ではない。ましてやマニュアルに従った管理(コントロール)はマネジメントの最下層部分にすぎない。
2つだけ例示。
ひとつは、バリューチェーン・マネジメント(VCM)。日本企業はこれまで単体(よくて連結)のマネジメントで過ごしてきたが、これからはVCMが必須になる。この場合、従来型のマネジメント=超生真面目な微細なマネジメントは百害になる。どうマネジメントするか。
ふたつめは、トップにスーパーマンを期待することは殆どできないとすれば、ミドルアップ・トップダウン型を徹底することが肝要と思われる。そのためにもミドルのスキル・アップ、リスキリングが極めて重要になる。キャリア採用ということだけで済まされる課題ではない。